FAQページ(よくある質問)の作り方!作成のポイントも紹介

こんにちは!楽テルコラム担当です。
FAQページ(よくある質問)を作成することで、クレームを減らし、顧客満足度を高められます。FAQページの作り方やユーザーに役立つFAQページのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
コールセンターの業務効率と対応品質の両方を上げるには
電話対応業務における大きな課題である「オペレーターの対応時間」や「オペレーターの対応品質のバラつき」。
これらの課題解決に有効なのが、クラウド型CRM・CTIシステムです。
着信時ポップアップやIVR(自動音声応答)、自動文字起こしなどの機能を活用することで、コールセンター業務の質と両方を、大きく改善できます。
クラウド型コールセンターCRMシステム「楽テル」資料請求はこちら(無料)
目次
FAQページ(よくある質問)が重要な理由とは?

商品やサービスを提供している事業者なら、FAQページ(よくある質問)は作成しておくほうが良いでしょう。次の理由から、FAQページは重要といえます。
- 顧客満足度を高めるから
- クレームを減らせるから
- 本来の業務に集中できるから
各理由について見ていきましょう。
顧客満足度を高めるから
ユーザーにとって、商品やサービスについての問い合わせは決して楽なことではありません。問い合わせ専用ダイヤルやメールフォームを探すだけでなく、実際に電話やメールでのやり取りをしなくてはいけないため、かなりの労力と時間がかかります。
FAQページがあれば、該当する内容を見るだけで問題を解決できることがあります。事業者に問い合わせる必要がなくなり、顧客満足度も高まるでしょう。
クレームを減らせるから
ユーザーが問い合わせをする場合、すぐに満足できる答えを得られるとは限りません。いくつもの部署をたらい回しにされたり、問題解決までに長い時間がかかったりすることがあります。
満足できる答えをすぐに得られないことに不満を感じ、クレームをつけるユーザーもいるでしょう。クレームを受けることは、担当者やオペレーターにとっても大きなストレスとなります。クレームを減らすためにも、適切なFAQを準備し、ユーザーが短時間で答えを得られるようにしておきましょう。
本来の業務に集中できるから
ユーザーからの問い合わせやクレームが多いと、本来の業務にかけるべき時間が減ってしまいます。業務に集中して取り組むためにも、FAQページを公開し、問い合わせやクレームが少ない状態にしておきましょう。
FAQページの作り方の手順

FAQページは、以下の手順で作成します。
- 質問を集める
- 収集した質問を分類する
- 質問の答えと関連情報をまとめる
- 質問と答えに間違いがないかチェックする
FAQページの作り方を、順を追って解説します。
1.質問を集める
まずは質問を集めます。電話やメールで寄せられた質問だけでなく、営業担当者や販売担当者が直接顧客や取引先から受けた質問もすべてまとめておきましょう。
2.収集した質問を分類する
次に収集した質問を分類します。商品を販売している場合なら、次のように質問を分類できるかもしれません。
- 商品の特徴(大きさ、重さ、他のバージョンとの違いなど)
- 商品購入に関する質問(購入方法、支払い方、販売店舗など)
- 商品の使い方に関する質問(操作方法、電源の入れ方、初期化の方法など)
- 商品の故障・不具合に関する質問(動かない、異音がする、初期不良など)
- その他(廃棄方法、商品に対する提案、販売員に対する意見など)
質問を適切に分類することが、より良いFAQページにつながります。ユーザーがいち早く知りたい情報を収集できるように、丁寧に分類をしてください。
3.質問の答えと関連情報をまとめる
質問に対して正確な答えを作成します。また、疑問に感じたユーザーに必要と思われる関連情報もまとめておきましょう。
たとえば、商品が動かないことについて問い合わせたユーザーなら、動かし方だけでなく、返品対象の場合の送付先や返品の手順についての情報も知りたいと考えられます。ユーザーにとって使いやすいFAQページを作るためにも、関連情報を充実させておくことが大切です。
4.質問と答えに間違いがないかチェックする
質問の答えが間違っていると、ユーザーを混乱させるだけでなく、顧客満足度が低下する恐れがあります。有用なFAQページに仕上げるためにも、答えに間違いがないかチェックしておきましょう。
ユーザーに役立つFAQページを作成するポイント

FAQページは、ユーザーの利便性を高めることを目的として作成します。ユーザーにとって役立つFAQページにするためにも、次のポイントに注目して作成しましょう。
- CRMデータを活用して質問を抽出する
- 複数の解決策を提案する
- 関連情報を紹介する
- 検索機能をつける
- 定期的に質問と解答を見直す
- FAQページの満足度を調査する
- FAQページへの動線を増やす
それぞれのポイントを説明します。
CRMデータを活用して質問を抽出する
ユーザーファーストのFAQページを作るためにも、質問の網羅性を高めておくことが必要です。顧客情報を管理するCRMを利用している場合は、今までの問い合わせをデータ化し、質問をまとめておきましょう。
コールセンター向けのCRMシステム「楽テル」なら、コールセンターに寄せられたユーザーのさまざまな質問をデータ化して整理できます。顧客満足度を高めるFAQページに仕上げるためにも、ぜひご活用ください。
複数の解決策を提案する
質問内容によっては、複数の解決策を提案するようにしましょう。
同じ質問であっても、ユーザーによって希望する解決方法が異なることがあります。ユーザーの希望に沿った解決方法を提示するためにも、想定される解決策をすべて紹介しましょう。
関連情報を紹介する
質問に関連する情報も紹介しましょう。
複数の疑問を抱いてFAQページにアクセスするユーザーもいます。また、FAQページで質問の答えを見てから、新たな質問が湧くかもしれません。関連情報として紹介すれば、ユーザーが再度FAQページで答えを見つける手間が省けます。
検索機能をつける
ユーザーが簡単に疑問を解消するためにも、FAQページに検索機能をつけるようにしましょう。検索機能がないと、ユーザーはFAQ一覧をすべてチェックする必要が生じ、質問の答えを得るまでに時間がかかってしまいます。
定期的に質問と解答を見直す
商品やサービスのバージョンが変わることで、質問に対する答えも変わることがあります。また、新商品や新サービスの提供を開始した時も、質問と答えを見直すことが必要です。定期的にFAQページを見直して、常に新しく正しい情報を提供できるようにしておきましょう。
FAQページの満足度を調査する
丁寧にFAQページを作成したとしても、ユーザーにとって使いやすいとは限りません。FAQページに対するユーザーの満足度を定期的に調査し、必要に応じて改善しましょう。
FAQページへの動線を増やす
ユーザーの疑問に素早く答えるためのFAQページですが、FAQページそのものが見つけにくく、利用されない可能性もあります。ホームページやSNS、取扱説明書などにFAQページを紹介し、動線を増やしておきましょう。
まとめ
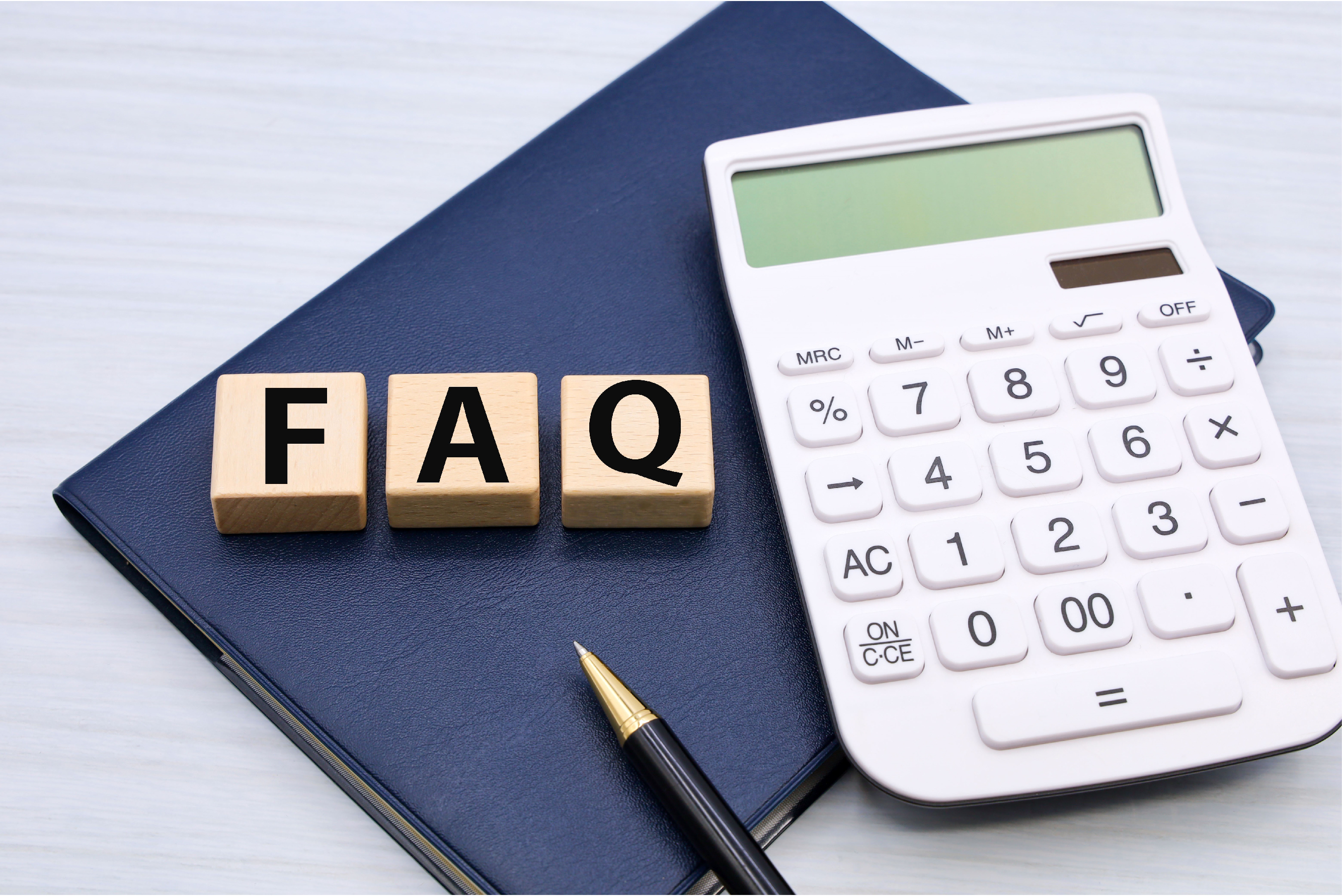
ユーザーにとって使いやすい商品やサービスを提供し、顧客満足度を高めるためにも、FAQページが必要です。CRMを使ってユーザーの質問を網羅すれば、ユーザーに役立つFAQページを作成しやすくなります。
CRMシステムをご検討の方には、楽テルがおすすめです。楽テルはオペレーター向けのCRMシステムのため、オペレーターに寄せられたユーザーの質問をすべてデータとして蓄積できます。利用料金は月額80,000円~、初期費用は150,000円~です。無料トライアルも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
最新記事
記事執筆者情報

楽テルコラム編集部
リスティング広告やFacebook広告の運用、プロダクトサイトのSEOなど、広くWEB施策に携わっています。前職では、世界トップクラスのシェアを誇るCRMシステムの導入支援を通して、様々な企業の業務改善に尽力していました。
楽テルのコラムではコールセンターやインサイドセールスにおける業務効率化・顧客満足度向上などの例をご紹介していきます!
好きな料理は「スパイスカレー」です。






